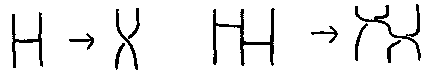あみだくじ
あみだくじの雑学 日本独特のくじ引き・・らしい
友人からの書簡 日本文学の達人より
あみだくじと私 初めて出会った時。覚えてる?
あみだくじとコンピューター ここにもいたのね。
あみだくじの雑学
あみだといえば阿弥陀。寺に囲まれて育った私としてはその名も気になっていたが、もともとは放射状に直
線を引き、真ん中に選ぶもの、外側に選んだ人の名を書いていたらしく、それが阿弥陀像の後光に似ている
ことから付いた名だった。
テーブルにイスとかじゃなく、床に円座になって協議していた様子が目に浮かぶようじゃありませんか。
はしご状になったのは後の話らしいが、この辺が今一つ資料が無くよく分からない。初めにこのルール
見つけた人は面白かっただろうなぁとは思うが。子供の頃は、あんなに曲がっても一つもだぶらずに
上と下が対応するのが不思議だった。
この辺は数学の組糸理論というのに関係し、それは群論というの(つるがやっていた。私はわけわかんない
・・)と深く関係するらしい。その結果は結び糸の研究に用いられる。(岩波数学事典を紐解いてみたところ、
組み糸、結び糸の説明が膨大で(T_T)、私にはうまく説明できる力量がない・・)
ともかく、線の間に入った「横線」は「その両脇の二本の線が互いに入れ替わる交点と同様」に考えられる
ので、平行に並べた糸をあっちこっちに引っ張って違う所に下ろしたのと同じで、結局ちゃんとだぶったり
せず、一対一に上下が対応するんだよ、という事(下図参照)。
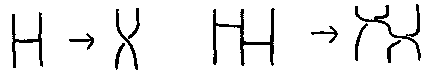
そういわれればまあそうなんだが、なんか中には途中で
出会った人とおんなじ道を行ってしまう人がいそうな感覚が、惑わせるんですよね。
友人からの書簡
(←この人は、日本文学を専攻し大学院では源氏物語の研究をしていた)
HPの医学生日記1年2学期「海の外のお話」の以下の部分を読んだ友人がくれたメール。
「あみだくじは日本独特のもの。(これで班の順番を決めていたら彼女は面白がっていた。順番を決める
とき、線に番号を引いてそれを隠して引かせることはするが、あのようにはしご状にはしない、」
これ、すごく惹かれるなぁ。なんか、「あみだくじ」って、そう考えると日本人の思考にマッチしてるって
気がする。選択肢と結果が一直線だけだった場合、「自分の意志」というものが全権を握っているけど、
あみだくじっていうのは、「これを選んではみたけど、どうなるかはあみだしだいなんだよね。」という
あなたまかせな、風まかせな、どこか無責任な(笑)、「諸行無常」を感じますね。
何をしても、結局、あみだで翻弄されるのが人生。引っ込んで世を斜めから見ちゃうモンね・・という
鴨長明の思想がプンプン臭う。それに、「春死なむ」ではなく、「願わくは・・・」をつけてしまう
西行とか(笑)あみだ・・・深いなぁぁぁ。あー、なんかいまモーレツに感動してます。
私は、自己責任の原理で生きる欧米人の生き方も好きだけど、でも、行着く先に願いを込めながら、
それでも、希望通りにいかないことも十分にわかりつつそれを楽しみ、あみだの行く先を目で追っていくと
いう、日本人の余裕と洒落のある生き方も好きですね。まぁ、そんな生き方をしている日本人も、
昨今は少ないでしょうが。
たしかになぁ〜って感心してしまいました。合理性だけなら、ちんたら曲がってないで、さっさと
結果をまっすぐ見ればずっと手間が無くて明快なわけですからね。もっとシビアな、緊張と不信を
はらんだ中でのくじならば、こうはならなかったかも。単に何かを決めるという実用的な部分だけ
でなく、一緒になって、運命を眺めつつたゆたっていってるような感じは確かにしますよね。
あみだくじと私
日本では未来永劫廃れないんじゃないかというぐらい日常に浸透しているあみだ。私が初めて目にしたのは
小学校。先生だったか、同級生だったか、黒板にすらすらと不思議な線を引き、それを引かせた。え〜っ、
そんなに線なんか入れて、ごちゃごちゃ曲がったら同じのを引く人が出ちゃうじゃない・・・と思った。
が!絶対だぶらないのだ!進行方向に後戻りしない、枝道は必ず曲がる、というただそれだけのルールで、
どうも一対一の直線群と同じ事になっているらしい!!(もちろんそんな意味のことを思っただけで、
こんな難しい言葉で考えたわけではない。解説は上のあみだくじの雑学参照)
ルールがシンプルなだけに、その魔法がすごいと思った。なんでかという「説明」をしたいと目を皿の
ようにして図を眺めたけど出来ない。目の前にはっきりと単純に起こっていることなのに、出来ない。
それを当たり前のように知っていた子達や先生を「文明の進んだ人を見る驚嘆の気持ち」で見た記憶がある。
うちの子供達は早くも保育園で覚えて来た。やはり気になるのか、お絵描きボードにせっせと書いては、
たどって喜んでいる。現在マイブーム状態で毎日毎日、下に色々な数字や、まる、バツ、リンゴ、顔、
ポケモンなどを書き、あみだくじを作成しては、ひいて〜ひいて〜と持ってくる。日本人だねぇ。
6才の方は必ず曲がる、と言うルールを一日ぐらいで飲み込んだらしいが、4才の方は、始めのうち
十字路のある格子状の線を引いて、交差点では適当に曲がって、あみだと称していた。それ違うって・・
(−−;)と時々助言しつつ、半月後にふと見ると、ちゃんと習得していた。
あみだくじ〜♪あみだくじ〜♪と楽しげに歌いつつ書いているが、それが大昔に明石家さんまが変な
「あみだくじばばぁ」というものに扮して歌っていた歌だとは、子供達は知る由もない。
「あみだくじ〜あみだくじ〜どれにしようか、あみだくじ〜引いてうれしいあみだくじ〜」ってへんな歌。
その旋律は日本の古い日常的な民謡の短調の調べ。いろり端の老婆が歌いついでいたような暗く平坦な
節回しだ。さんまやあの扮装の雰囲気とは対極な面白さはあったのだろうが、やたら世間のツボにはまって
流行ったという下地を様々な方向から勘ぐると面白い。
あみだくじとコンピューター
インターネットでも調べてみようと「あみだくじ」を検索すると、出てくる出てくる「あみだくじ作成ページ」
「あみだくじゲーム」。見てみると、選択肢の数や横線の数を入力すると画面上にあみだくじを作って
くれるとか、線を選ぶと、辿っていけて、何等賞!と出来るとか・・・。確かにルールが単純だし、
使うのは直線だけだし、プログラムを作るのは簡単だが、何でこんなにあるの(−−;)?プログラミングの
練習に作る人が多いのかな?誰がどのように利用しているのか??
これも、外国の人が見たら大変オリエンタルな、というかジャポネスクな光景なんだろうか。